
「赤・白・ロゼのワインって、どう違うの?」と迷ったことはありませんか?
色の違いは見た目だけでなく、味や香り、料理との相性にも影響します。
本記事では、ワイン初心者にもわかりやすく、色と味の関係や選び方を丁寧に解説。
「自分に合うワインを知りたい」「選び方のコツを知りたい」方にぴったりの内容です。
この記事を読むことで、ワイン選びに自信が持て、もっと自由に楽しめるようになります。
ワインの色が違う理由とは?
ワインを選ぶとき、まず目に入るのがその色の違いです。
赤ワイン、白ワイン、ロゼワイン──それぞれの色には意味があり、味わいや香り、さらには相性の良い料理にまで影響を与えています。
では、ワインの色は何によって決まるのでしょうか?ここでは、色の違いが生まれる3つの主な理由をご紹介します。
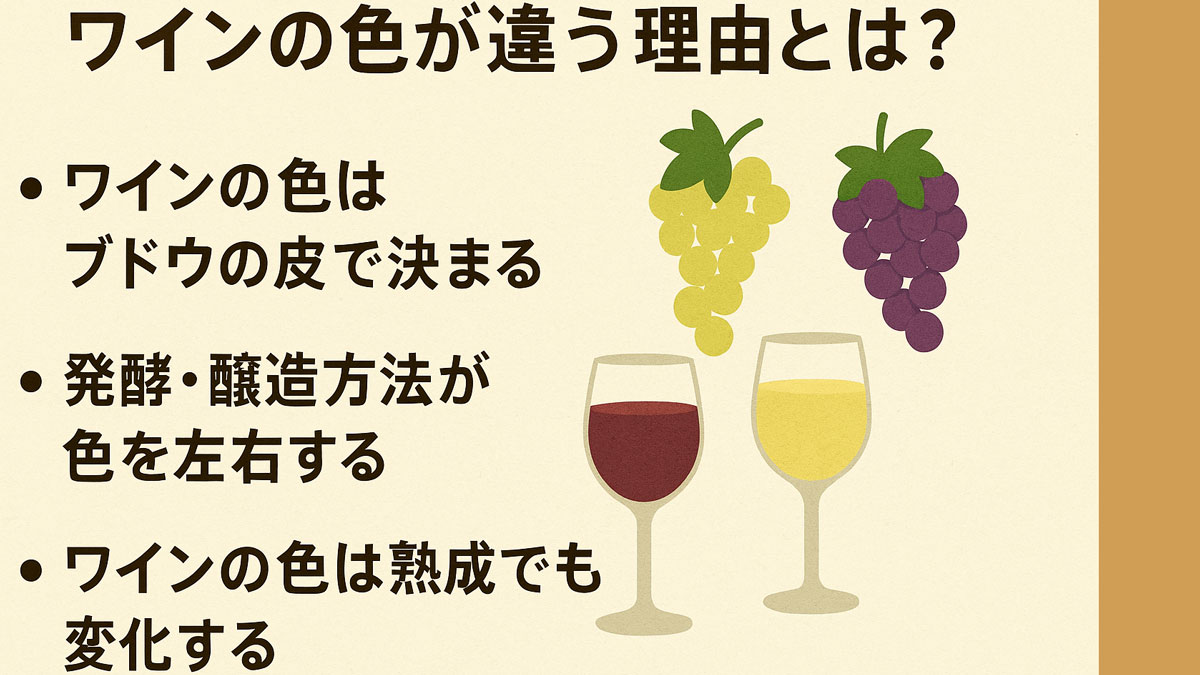
ワインの色はブドウの皮で決まる
まず第一に知っておきたいのは、ワインの色の多くは「ブドウの皮」から抽出されるという点です。
赤ワインに使われるブドウは、果肉は白くても皮が濃い紫や赤のものが多く、醸造の過程でその色素がワインに移ります。
一方、白ワインは果汁だけを使用して造られるため、皮の色に関係なく透明感のある色合いになります。つまり、同じ品種のブドウでも、皮を一緒に発酵させるかどうかで色が変わるのです。
ロゼワインはその中間で、黒ブドウの皮を短時間だけ果汁に浸して淡いピンク色を引き出します。この皮の接触時間が、ロゼの色合いや風味の鍵を握っています。
発酵・醸造方法が色を左右する
色の違いに大きな影響を与えるのが、発酵と醸造の方法です。
赤ワインは、果汁と皮、種を一緒に発酵させる「マセラシオン(醸し)」という工程を経て色素とタンニンを抽出します。この方法によって、濃いルビー色から深いガーネット色のワインが生まれます。
一方、白ワインはブドウを破砕してすぐに果汁だけを取り出し、澄んだ状態で発酵を始めます。そのため、黄金色や淡い緑がかった色調になります。
ロゼは、発酵の初期段階で果汁から皮を取り除く「セニエ法」や、赤と白をブレンドする方法(ヨーロッパでは原則禁止)など、スタイルによって造り方が異なります。
ワインの色は熟成でも変化する
ワインは時間とともに熟成し、色にも変化が生まれます。特に赤ワインは、若いうちは紫がかった鮮やかな色をしていますが、熟成が進むとレンガ色や茶色に近づいていきます。これはポリフェノールが酸化することで色調が変化するためです。
白ワインも、若い頃は淡いレモン色ですが、熟成により黄金色に深まり、まろやかな味わいへと変化します。
このように、ワインの色は「今飲み頃なのか」「熟成が進んでいるのか」の判断材料にもなります。色を見ることで、味や香りの変化もある程度予測できるのです。

ワインの熟成による色の変化を示した図解(16:1サイズ)です。
赤ワインと白ワインそれぞれが、0年〜15年の熟成を経てどのように色合いが変化していくのかが一目でわかります。
-
上段:白ワイン → 若いと薄い黄色、熟成で黄金色へ
-
下段:赤ワイン → 若いと紫がかり、熟成でレンガ色や茶色がかる
まとめ
ワインの色は見た目だけでなく、味わいや香り、さらにはその背景にある製造過程まで反映しています。
-
ブドウの皮の色と接触時間
-
発酵・醸造の方法
-
熟成による酸化の影響
これらの要素によって、ワインの個性が色に現れます。
次にワインを選ぶときは、色にも注目してみてください。見た目から楽しむことで、ワインの世界がぐっと広がりますよ。
赤ワインの特徴と楽しみ方
赤ワインは、その深い色合いや重厚な味わいから「大人の飲み物」というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。しかし、その個性は品種や製造方法によってさまざま。ここでは、赤ワインの色と味・香りの関係から、料理との相性、そしておすすめの品種までをわかりやすくご紹介します。

赤ワインの色と味・香りの関係
赤ワインの色は、ブドウの皮から抽出されたアントシアニンという天然色素によって生まれます。若い赤ワインは紫がかったルビー色で、熟成が進むとレンガ色やオレンジがかった色調へと変化していきます。
この色の濃さはタンニンの量とも関係しており、濃いワインほど渋みが強い傾向にあります。また、果実味の強いもの、スパイス香が感じられるもの、さらには樽熟成によるバニラやチョコレートのような香りを持つものなど、香りの多様性も赤ワインの魅力です。
どんな料理と合う?赤ワインのペアリング例
赤ワインは、味わいの濃さや渋みによって合わせる料理が異なります。以下の表は、赤ワインのタイプごとにおすすめの料理をまとめたものです。
| 赤ワインのタイプ | 味の特徴 | 合わせたい料理例 |
|---|---|---|
| ライトボディ | 軽め、フルーティ | チキンのトマト煮、ピザ、パスタ |
| ミディアムボディ | バランス型 | ハンバーグ、すき焼き、グリル野菜 |
| フルボディ | 濃厚で渋みが強い | ステーキ、ラムチョップ、ビーフシチュー |
特に脂の多い肉料理と赤ワインは好相性です。タンニンが脂を洗い流し、口の中をさっぱりさせてくれるため、料理とワインの風味がより一層引き立ちます。
おすすめの赤ワインと品種
赤ワインにはさまざまなブドウ品種がありますが、以下の品種は特に日本でも人気が高く、初心者にもおすすめです。
-
カベルネ・ソーヴィニヨン:しっかりとした骨格と渋み。ステーキとの相性抜群。
-
ピノ・ノワール:軽やかで繊細な味わい。和食や鶏肉料理にも合いやすい。
-
メルロー:まろやかで果実味豊か。初心者におすすめの飲みやすさ。
-
シラー(シラーズ):スパイシーで力強く、肉料理全般と好相性。
これらの品種はスーパーやワイン専門店でも手に入りやすく、価格帯も幅広いため、自分の好みに合わせて選ぶことができます。
まとめ
赤ワインは、色合いや香りから得られる情報がとても多く、料理との組み合わせ次第でその魅力は何倍にも広がります。
-
色の濃さで味わいや渋みが想像できる
-
香りは熟成や樽によって大きく変化する
-
肉料理との相性が抜群で、品種によって合わせ方も異なる
赤ワインの世界は奥深く、知れば知るほど楽しみも増えていきます。ぜひ、色や香り、料理とのペアリングを意識しながら、あなたにぴったりの一本を見つけてください。
白ワインの特徴と楽しみ方
赤ワインに比べて軽やかで爽やかな印象を持つ白ワイン。暑い季節や魚料理と合わせて楽しむ人も多いですが、実はその種類や味わいは非常に幅広く、奥深い魅力があります。ここでは、白ワインの色味や味わいの特徴、タイプ別の違い、料理との相性について紹介します。
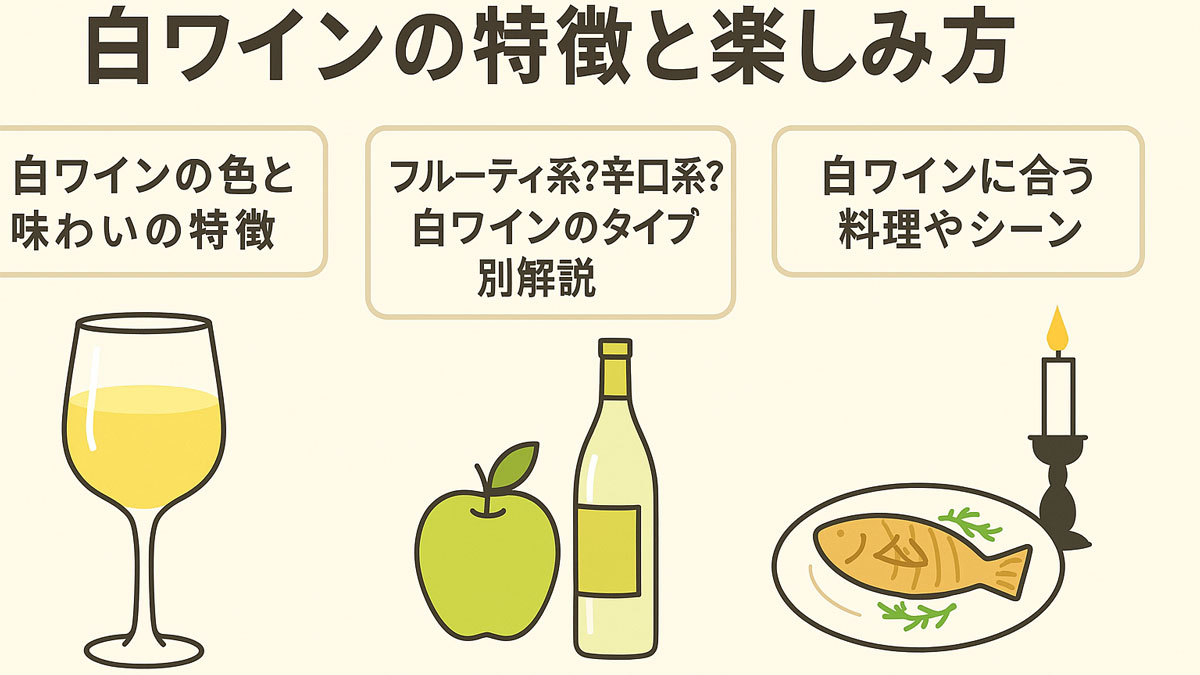
白ワインの色味と味わいの特徴
白ワインは、透明感のある淡いイエローから黄金色まで、色の幅があります。一般的に、色が淡いほど若くて軽快な味わい、濃い色合いほど熟成が進み、コクのある風味を持っていることが多いです。
味わいの特徴としては、酸味が主軸になっており、フレッシュでフルーティな印象を与えるのが白ワインの魅力。柑橘系や青リンゴのような爽やかな香りから、熟成によるハチミツやナッツ香まで、香りの変化も楽しめます。
フルーティ系?辛口系?白ワインのタイプ別解説
白ワインにはさまざまなスタイルがありますが、大きく「フルーティ系」と「辛口系」に分けられます。
| タイプ | 味わいの特徴 | 主な品種 | おすすめのシーン |
|---|---|---|---|
| フルーティ系 | 甘みを感じるフルーツ感 | モスカート、リースリング | デザートや軽食とともに |
| 辛口系 | キレのある酸味、すっきり感 | ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ | 食中酒として万能 |
たとえば、リースリングは香りが華やかで甘酸っぱく、食前や軽食にぴったり。一方、シャルドネは果実味と酸味のバランスが良く、幅広い料理に合わせやすい万能型です。
白ワインに合う料理やシーン
白ワインはその爽やかさから、魚介類や軽めの料理と特に好相性です。以下はシーン別のおすすめペアリング例です。
| シーン | 合わせる料理 | おすすめワイン例 |
|---|---|---|
| 家庭の和食 | 鯛の塩焼き、天ぷら、冷ややっこ | 辛口のシャルドネ |
| パーティーや前菜 | カプレーゼ、シーザーサラダ | ソーヴィニヨン・ブラン |
| デザートタイム | チーズケーキ、フルーツタルト | 甘口のモスカート |
また、冷やして飲むことができるのも白ワインの魅力の一つ。暑い季節には特に重宝され、カジュアルなピクニックやアウトドアでも楽しめます。
まとめ
白ワインは色合いや香り、味わいに繊細な変化があり、その多様性こそが魅力です。
-
酸味と香りでフレッシュさを演出
-
フルーティ系と辛口系で味わいに大きな差がある
-
和食からデザートまで、幅広い料理と相性が良い
日常の食卓から特別なひとときまで、白ワインはさまざまな場面で活躍します。ぜひ、色や香りを感じながら、自分好みの白ワインを見つけてください。
ロゼワインの魅力と特徴
赤ワインと白ワインの“中間”とされるロゼワイン。その見た目の美しさや、軽やかで親しみやすい味わいから、近年日本でも人気が高まっています。しかし、ロゼワインの魅力はそれだけではありません。ここでは、ロゼワインの製法や色合いと味の関係、料理との合わせ方について、わかりやすく解説します。

ロゼはどうやって造られる?
ロゼワインは、見た目こそ赤と白の“あいだ”ですが、れっきとした独自の製法を持っています。主な造り方は3つ。
-
セニエ法
赤ワインの発酵初期に、果汁の一部だけを抜き取り、短時間だけ皮と接触させて造る方法。フランスのプロヴァンス地方などでよく使われます。 -
直接圧搾法
黒ブドウを白ワインのように圧搾して、ほんのり色づいた果汁で造る方法。繊細でやさしい味わいに。 -
ブレンド法
赤ワインと白ワインを混ぜて造る方法。ただし、これはEUなどでは原則禁止されており、スパークリングワインに限られるケースが多いです。
ロゼワインは単なる“混ぜ物”ではなく、丁寧な製法で生まれたスタイルであることがわかります。
色合いからわかるロゼの味の幅
ロゼワインは、淡いピンクからサーモン色、鮮やかなローズ色まで、色のグラデーションがとても豊かです。そしてこの色味が、味わいにもある程度リンクしています。
-
淡いピンク:軽やかでフレッシュ、酸味が主体
-
中間色のサーモンピンク:果実味と酸味のバランスが良く、ややふくよか
-
濃いロゼ(ローズ色):赤ワインに近いしっかりしたコクや渋みも感じられる
つまり、色を見ることで、そのロゼワインの味わいの傾向がわかるのです。初めて選ぶなら、淡めの色から試してみるのもおすすめです。
食事との合わせ方やシーン活用例
ロゼワインの強みは「どちらにも寄れる」汎用性の高さ。赤のコクと白の爽やかさを併せ持つため、幅広い料理やシーンで活躍します。
| シーン | 合う料理 | おすすめのロゼタイプ |
|---|---|---|
| ホームパーティー | チーズ、シャルキュトリ、パエリア | サーモンピンク系ロゼ |
| お花見・屋外BBQ | 唐揚げ、焼き鳥、ポテト | 濃いめのロゼ |
| 夏のランチや軽食に | サンドイッチ、カプレーゼ | 淡い色のロゼ(冷やして) |
さらに、見た目の華やかさから、ギフトや乾杯のシーンにもぴったり。食卓を明るく彩りたいときには、ロゼが最適な選択肢になるでしょう。
まとめ
ロゼワインは、その色合いの美しさだけでなく、味わいや活用シーンの幅広さが魅力です。
-
製法により繊細な香りと味が生まれる
-
色で味の傾向がある程度わかる
-
赤・白どちらの料理にも合わせやすく、シーンを選ばない
赤や白よりも自由で、多様性のあるワイン──それがロゼワインです。ぜひ、日常の中で気軽に取り入れて、その魅力を味わってみてください。
色から楽しむワインの選び方
ワイン選びに迷ったとき、「ラベル」や「価格」だけで選んでいませんか?実は、ワインの“色”を見るだけで、ある程度その味わいや香りの特徴を読み取ることができるのです。視覚から楽しめるワインの世界。ここでは、色をヒントにした選び方のコツをご紹介します。

色でわかる「味の濃さ」や「香りの傾向」
ワインの色は、その味の濃さや香りのタイプを知るための“サイン”です。
-
赤ワイン
濃い紫~ガーネット色 → 渋みが強く、どっしりした味わい
淡い赤色 → 軽やかでフルーティな印象 -
白ワイン
薄いイエロー → 爽やかでキリッとした酸味
黄金色に近い → コクがあり、熟成された香りを感じる -
ロゼワイン
淡いピンク → フレッシュで飲みやすい
濃いサーモン色 → 果実感があり、少し赤ワイン寄りの味わい
このように、色の濃さや透明感が、そのまま味の傾向を映し出していると考えると、選ぶときの大きな手がかりになります。
シーン別・色別のおすすめワイン
ワインは、飲むシーンに合わせて選ぶとより楽しめます。下の表では、代表的なシーンごとに、ぴったりな色合いのワインを紹介しています。
| シーン | 合うワインの色合い | ワインのタイプ例 |
|---|---|---|
| 夏のランチ | 淡い白、淡いロゼ | ソーヴィニヨン・ブラン、ロゼ |
| 特別なディナー | 濃い赤、黄金色の白 | カベルネ・ソーヴィニヨン、熟成シャルドネ |
| 家族との食卓 | 中間色の赤、淡い白 | ピノ・ノワール、リースリング |
| アウトドア・BBQ | 濃い赤、濃いロゼ | ジンファンデル、グルナッシュロゼ |
色で選ぶことで、その場にぴったりの“雰囲気”も演出できるのが、ワインの面白いところです。
初めてのワイン選びに迷ったら?
初心者にとって、ワイン売り場は選択肢が多すぎて迷ってしまいがち。そんなときは、まず「色から選ぶ」ことをおすすめします。
-
明るく澄んだ色 → 軽くて飲みやすいワインが多い
-
濃く深い色 → 香り豊かで余韻のある本格派が多い
さらに、冷やして飲みたいときは白や淡いロゼ、常温でじっくり味わいたいときは赤を選ぶのもポイントです。
店頭で実物を見るのが難しいときは、ラベルの裏や販売ページに書かれた「色調の説明」や「味の強さの目安」も参考になります。
まとめ
ワインの色は、単なる見た目以上に多くの情報を与えてくれるヒントです。
-
色で「味の濃さ」や「香りの方向性」がわかる
-
シーンや料理に合わせて、色で選ぶと失敗しにくい
-
初心者はまず「色→味わい→好み」の順で楽しむのがコツ
視覚で楽しみながら、自分に合ったワインを見つける――それが、色から始めるワイン選びの魅力です。ぜひ次回のワイン選びに、色のヒントを活かしてみてください。
まとめ|ワインの色の違いを知って、もっと楽しもう
ワインをもっと楽しむための大きなヒント──それは「色」にあります。赤、白、ロゼ。それぞれの色には、ブドウの品種や造り方、味わいや香りの違いが反映されており、見るだけでそのワインの個性を感じ取ることができます。ここでは改めて、赤・白・ロゼそれぞれの魅力を振り返りつつ、色から楽しむワインの世界をまとめてみましょう。

赤・白・ロゼ、それぞれの魅力
赤ワインは、深みのある味と力強い香りが特徴。タンニンの渋みが肉料理とよく合い、しっかりとした食事の時間に最適です。熟成によって味も香りも豊かに変化するため、時間の経過を楽しむワインとしても人気です。
白ワインは、爽やかな酸味や果実味を感じやすく、魚介や野菜料理との相性が抜群。冷やして飲むことで清涼感が増し、暑い季節や前菜とのペアリングにも重宝されます。
ロゼワインは、赤と白の“いいとこ取り”。華やかな色合いとバランスの良い味わいで、シーンを選ばず楽しめる万能型です。近年では、その見た目の美しさからパーティーやギフトにも人気が高まっています。
色から始める、ワインの新しい楽しみ方
「どれを選んだらいいかわからない」と感じたときこそ、ワインの“色”に注目してみましょう。たとえば…
-
淡い色合いのワイン → 軽やかで飲みやすい
-
濃く深い色のワイン → 味に厚みがあり、余韻が長い
-
ピンク系のロゼ → 見た目も華やかで、気軽に楽しめる
こうした視覚的なヒントをもとに、自分の好みやその日の気分に合わせたワインを選ぶことで、楽しみ方がぐっと広がります。
また、家族や友人と一緒に飲むときには、「色の違いを見比べてみる」のもおすすめ。それぞれの色の中にある個性に気づくことで、会話も自然と弾み、ワインがもっと身近に感じられるでしょう。
おわりに
ワインは「難しそう」と思われがちですが、色から味や香りを想像するだけでも、十分に楽しめる飲み物です。見て楽しい、飲んで美味しい、そんな五感を使った体験こそが、ワインの魅力。
ぜひ今後は、ラベルを見るだけでなく、グラスの中の色にも注目してみてください。きっとあなたらしいワインの楽しみ方が見つかるはずです。
出典情報
本記事の内容は、以下の信頼性ある情報をもとに編集・構成しています。
-
日本ソムリエ協会「ワイン検定テキスト 初級編」
-
Wine Folly(https://winefolly.com/)
-
『ワインの基礎知識』(著:葉山考太郎/集英社)
-
各種ワイナリー公式サイト・商品情報ページ
※情報は2025年3月時点のものです。





